
最近の「信仰の証」や「感動体験」や「日々考える事」など・・・自由に投稿してください
来間 幸夫さんからの投稿
日本宣教に貢献した教会音楽の主流・聖歌の流れと
和田健治先生との交流
2025年9月27日
今年2025年3月5日に、中田羽後先生の後継者である和田健治先生が90年の生涯を終え、天に凱旋された。和田先生とは、1967年10月に日本武道館と後楽園球場で開催されたビリーグラハム国際大会で、聖歌隊に参加した際、初めてお会いした。和田先生は聖歌隊の指揮者として活躍されていた。

和田健治先生と私
後楽園球場での宣教大会では、聖歌「キリストには代えられません」の作曲者:ベバリー・シェアさんが独唱された。感動的でした。聖歌隊では、その他「輝く日を仰ぐとき」等が賛美され、決心の招きの時には、「いさおなき我を」が流れ、若者を中心として5,000人もの決心者が続々と、ビリーグラハム博士の立っている講壇の周りのグラウンド中央に降りてきた。素晴らしい神様のみわざの情景でした。(4日間で、のべ20万人、決心者1万5千人という)

ビリーグラハム宣教大会
その後私は、和田先生が主宰する「東京クリスチャン・コワイア」に参加して、「ヘンデルのメサイア」合唱団に加わり、テナーパートとして指導を頂いた。明治学院大学のチャペルでの全国教会音楽講習会や聖歌独唱発表会にも参加させて頂き、数多くの聖歌を学んだ。幹事の末端として、会計の担当を永年務めさせていただいた。
メサイア公演は、東京文化会館大ホール、日本教育会館一ツ橋ホール、共立講堂、浅草公会堂などで計50回の公演を行った。音楽・声楽を学んでなく、全くの素人であった私が「ヘンデルのメサイア」合唱団に加わり歌う事ができ、それもパートリーダーの一人として用いて下さったのも、ひとえに和田先生のご指導のお陰であり、神様のご恩寵でした。感謝主!


また一方、昨年7月15日に御茶ノ水クリスチャンセンター8階チャペルで、「中田羽後先生召天50周年記念会」を開催した。その1年前に、中田羽後先生の功績を残そうとして、「中田羽後記念聖歌記念館」を設立するためとして、クラウド・ファウンディングを計画した。立ちあげたものの、私共の祈り不足と準備不足により頓挫した。中田羽後師のドキュメンタリー映画を作ることは、紆余曲折あったが、何とか成功した。記念会当日には、中田羽後師の生涯を紹介するドキュメンタリー映画を上映できた。また、参加者にドキュメンタリー映画のDVDをお渡ししました。
中田羽後先生

その他、5か所の教会の聖歌隊の合唱発表会も行った。当初、聖歌隊合唱大会を企画していたが、その域までは到達できなかった。
更に、植木先生や宋先生はじめ5名の独唱者の賛美もあり、クリスチャン新聞のT兄の取材により、クリスチャン新聞に、「中田羽後先生召天50周年記念会」の開催の記事を載せて頂いた。
和田先生の召天後、(有)聖歌の友社は、夫人和田靖子さんの長男の慎一氏がその後継者として選出された。日本教会音楽研究会及び聖歌委員会の代表は、それにふさわしい後継者が与えられる迄、暫定的に小生がその任を受けることになった。

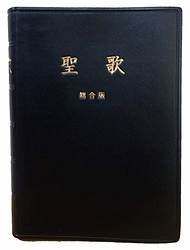
「聖歌(総合版)」に関しては、旧聖歌を正式に後継した聖歌として、今後とも、日本福音宣教の拡大及び福音主義教会の音楽向上の為に、大いに活用され、歌い継がれるべき大切な財産です。
幸い、数年前に、「聖歌プレヤー」が発売され、更に、一昨年よりスマホ・アプリに、標準伴奏による全818曲がアップされた。付録として、独唱10曲が含まれ、東京クリスチャンコワイアによる「ハレルヤコーラス」も収録されております。(月380円でいつでも・何度でも818曲が堪能できます。)
特に、教会での各種集会で、奏楽者の代わりに役立ちます。 私も、スマホ聖歌プレヤーをアップしており、今年、三鷹のチームセンターで開催された「カレブの会新年リトリート」で、賛美の際に用いられた。

ぜひ、一人でも多くの方に「スマホ聖歌プレヤー」を個人的にダウンロードして、あらゆる機会にご活用して下さるように、お奨めいたします。 素晴らしい聖歌・賛美歌に出会えることができ、心慰められます。また、より豊かなクリスチャン生活に役立つと思います。私の信仰は、聖歌を歌う事により恵まれ、守られたと回想し、感謝いたしております。
また、中田羽後先生、和田健治先生に心より感謝いたします。 感謝主!
参考までに
「聖歌」の流れの概略を下記に記述します
明治30年に編集者は
笹尾鐵三郎、松尾菊太郎で、B・Fバックストンにより発行された「救の歌」から始まり、三谷種吉、中田重治、坂井勝次郎、中田羽後そして和田健治により編集され
128年延々と継承された。
発行所は、松江市赤山から始まり、中央福音傳道館、聖書学院、東洋宣教會出版部、日本聖歌協会、日本福音連盟、いのちのことば社、聖歌の友社である。
現在は、「聖歌の友社」が継承している。
詳細は、聖歌の友社のホームページ
http://www.seikanotomo.jp/index.html
をご参照ください。
平野 誠さん からの投稿です。
『改めて知った母の愛』
2024年12月31日
三ツ境教会の会員だった時のことです。
金子保雄さんという方が受洗しました。教会の「証し集」に書かれた文章を読んで驚きました。「私は昭和10年に、鶴見の生麦小学校で教員生活をスタートしました」とありましたが、母も生麦小学校に教員とし勤めていて昭和10年に私を産んでいたのです。
家に帰って母にこの証しを見せたところ驚いて、「3年間ご一緒だった方よ!」と言いました。次の日曜日、礼拝に出席し、金子さんと何十年ぶりかのご対面をしました。このことがきっかけになり、金子さんの家で開かれていた聖書の勉強会に、私と一緒に参加するようになりました。
そしてもう一つ、忘れられない出来事がありました。
今は「産休補助教員制度」というのがあって、お産をする先生を主に退職した先生が一定期間補助する制度がありますが、当時はそれがなかったので、母は私をおんぶして小学校へ通っていたのです。これも不思議なことですが、両親の結婚の仲人をされた酒井さんという方のお宅が学校の近くにあったのです。母は勤務が終わると時々立ち寄っていたようです。
酒井さんの家にも女の子が生まれていました。母が仕事と子育ての両立が大変だと話すと、「じゃあ、誠ちゃんを預かってあげますよ」ということになったそうです。
私が幼稚園に通っていた頃、「あんたはあたしのオッパイで大きくなったのよ」と言われ、照れ臭かったのを覚えています。実はこの酒井さんがクリスチャンだったのです。鎌田の病院に入院していた時、鎌田の教会の会員だった看護婦さんの導きで信仰を持たれました。
母が亡くなる少し前に、この頃の話をする機会がありました。母は言いました。
「教壇に立っていて、酒井さんのお宅であんたがどうしているかと思うと、不思議に胸がぬれてくるのよ」
この時、改めて母の愛を知ったのでした。そして私は頬がぬれました。
金子さん、酒井さんと母との出会い。クリスチャンの酒井さんに育ててもらったこと、神様の大きな愛のご計画を知りました。
2023年12月25日記
高齢者の健康法
来間 幸夫 2022/3-17

説明
*17のねこ体操:床に仰向けに寝て、前足(両手)と後足(両足)を天に向けて、ぶらぶらさせる運動です。加えて、猫のように床に前足・後足とも、四つんばりになり、背中を持ちあげたり、背中をひっ込めたりする運動です。
*17の天つき体操:両足を開いて地面に踏ん張り、両手で重量挙げのように、天(空)に向かって、天を持ち上げるような体操です。両手をあげたり、おろしたりします。両手で天を突き上げる格好です。(戦前の体育にあったようです)
*18のお相撲体操:土俵でのお相撲さんのしぐさそのものです。四股を踏む体操です